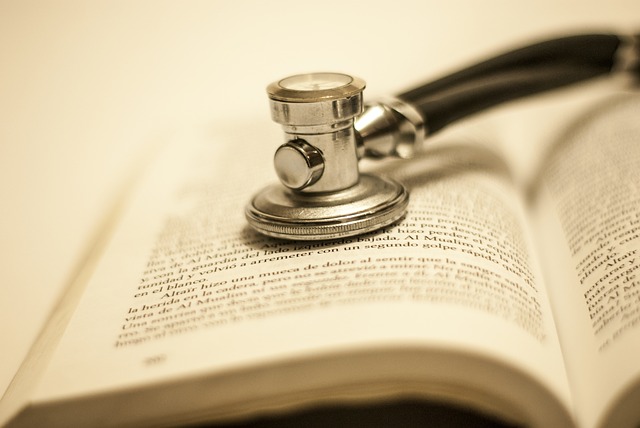医学科の大きな試験について
医学部に入った後、
医学部生を待ち構えている試験といえばまず思いつくのが
医師国家試験だと思いますが、
実はほかにも大きな試験がいくつかあります。
その名もCBT(シービーティー)とOSCE(オスキー)です。
今回はそのうちのOSCEについて紹介していきたいと思います。
OSCE
OSCEは全国の医学部生が受ける共用試験のひとつです。
「共用試験とは、わが国のすべての医師及び歯科医師育成に携わる医学部・歯学部が、
試験課題を作成、かつ共有して実施することで、
国民・社会に対し医学部・歯学部の卒業生の質を保証するための試験です。」
と、公益財団法人医療系大学間共用試験実施評価機構の発行する
『共用試験ガイドブック』に記載されています。
一定以上の知識と診察能力を有していることを
この共用試験の合格によって担保しているので、
この試験を受からないと病院実習には参加できません。
実習に参加できないということは、
進級できないということになります。
つまり、不合格の瞬間、留年が確定してしまうというのです。
(両試験ともに一度だけ再試験が受けれます)
医学系の共用試験(医学科の生徒が受けるもの)は、
- 臨床実習開始前のComputer Based Testing(CBT)
- 診療参加型臨床実習開始後客観的臨床能力試験(Pre-CC OSCE)
- 診療参加型臨床実習開始後客観的臨床能力試験(Post-CC OSCE)
の三種類から構成されます。
(歯科学生の受ける共用試験とは異なります)
その名の通り①、②は3年生か4年生の臨床実習前に行われ、
③は臨床実習の終わった6年生で行われます。
Pre-CC OSCEは学生が臨床実習を開始するにあたって
具備すべき必須の臨床能力を兼ね備えているかを確認する試験です。
必要最低限の共通標準課題として、
1)医療面接…模擬患者さんを相手に10分間の医療面接を行います。
2)頭頸部…頭頸部における異常の有無を診察します。
範囲としては頭、眼、耳、鼻、口、咽頭、唾液腺、リンパ節など。
3)胸部、全身状態とバイタルサイン…胸部の異常と呼吸脈拍の不整などの有無を診察します。
4)腹部…腹部の異常の有無を診察します。消化管、肝臓、脾臓などが範囲になります。
5)神経…感覚や運動の異常の有無を診察します。
6)基本的臨床手技、救急、脊柱、四肢
があり、この6課題が試験として実施されます。
7課題以上実施する大学もあるようです。(最大9課題)
OSCEは非常に厳正に行われる試験なので、
大学の教員だけでなく、機構から派遣された他大学の先生が来られます。
医療面接以外の課題では、模擬患者を医学科の低学年学生が担当します。
OSCEの一か月前ほどの時期に、
医学科、看護学科の生徒に有志の募集がかかります。
数年後に控えるこの試験の全体像を把握しておくために
OSCEで模擬患者を経験しておくことをお勧めします。
(少しの報酬が出る場合もあります)
最後に
今回はOSCEについて紹介してきました。
実際に病院実習に入った時に重要な手技を確かめる試験なので、
ちゃんと習得していないと大変なことになります。
一方で、実のところOSCEで進級できなくなることは非常にまれです。
ふつうに勉強し、練習をしていれば
不合格になることを恐れるほどの試験ではありません。
(重要な試験であることは変わりありませんが…)
今回は以上です。See you~♪