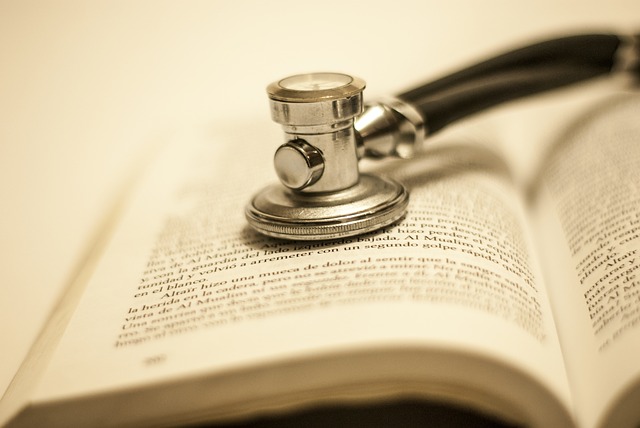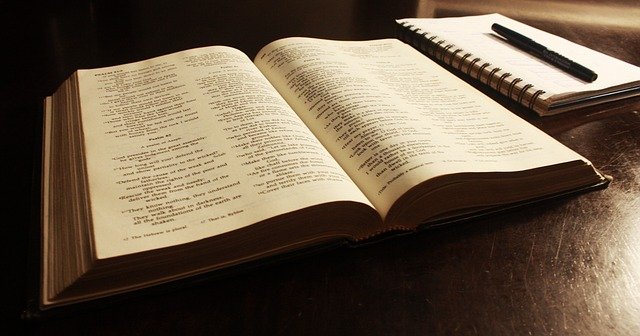今回は医学科入試において必要な教科、科目について紹介していこうと思います。
医学科を受験する際には高校の文理選択のみならず、理科選択においても
気を付けないといけない部分がいくつかあるので、
その部分にも注意しながら進めていきたいと思います。
まず前提条件として、
文理選択では理系を選択しておく必要があります。
以降は理系選択をしているものとして話を進めていきたいと思います。
『数学・理科』
一般的に理系科目と呼ばれる科目の試験になります。
これらの科目は共通一次試験でも二次試験でも、
医学科受験のメインとなってくることはいわずもがなです。
受験勉強においてもっとも労力と気合を費やす科目たちであろうと思います。
二次試験の数学は数Ⅲまでが必須です。
特に単科医科大学の試験では数Ⅲの難しい問題が出題される傾向にあります。
これは単科医科大学だと、総合大学と違い、
その入試問題を解くのは医学科志望の生徒のみであるため
医学科志望の生徒以外の受験に対する配慮が不要であることで
難易度を上げられていることが
大きく影響していると考えられます。
数Ⅲの問題は考える力に加えて計算力も必要になるので、
日々の鍛錬がものを言う分野であることは間違いありません。
理科は物理、化学だとどの国公立大学でも受験できますが、
生物だと受験できない大学がごく一部あります。
また、ほとんどの大学で地学を二次試験に使うことができないため、
高校の理科選択には十分注意が必要となるでしょう!!
また、二次試験において理科が課されない大学が少数ながら存在します。
それらの大学のみを志望する場合でも、
私立大学や後期入試のことも考えると、
理科を捨てることは医学科入試においてはあまり得策とは言えないでしょう。
『英語』
英語は共通一次試験、二次試験おいて必須です。
長文読解はもちろん、
和文英訳、英文和訳、自由英作文の有無や文字数などで
各大学それぞれの特徴が現れます。
受験生期間の早い段階で志望大学の過去問を見て
特徴を確認しておくべきでしょう。
和文英訳、英文和訳、自由英作文は
練習と添削を繰り返すことで
徐々に上達していくものです。
一日で完成するものではありません。
『国語』
共通一次試験では必須である一方で、
二次試験ではほとんどの大学では課されない教科の代表格です。
国公立では、東大、京大、名大、山形大のみで二次試験においても課されています。
配点としてはほかの教科に比べて比較的小さいですが、
その分、合否を分ける微妙な差となる可能性はあるでしょう。
先に述べた大学を受けないのであれば、
国語の勉強は共通一次試験レベルで十分といえるでしょう。
つまり記述問題の練習する必要はないということです。
決して勉強すべきでないというわけではなく、
他教科の記述問題や小論文に役立つと思うので、
国語が好きで勉強したい人や、他の教科に余裕のある人は、
やっておいても無駄になることはないでしょう。
『社会』
共通一次試験のみで課される科目です。
二次試験で社会を課している大学は現段階では存在していません。
つまり、医学科を目指すうえで
共通試験以上の知識が問われることはありません。
大学によっては公民での受験が認められていないところがあるので、
社会科選択の際は注意しましょう。
主要3つ(日本史、世界史、地理)はどの大学においても受験可能です。
『小論文』
一部の国公立大学(主に後期試験)や私立大学で課される試験です。
得点化するかしないは大学によって異なりますが、
国公立の前期試験における小論文が得点化されることは少なく、
あくまでも医師になるうえで不適切な思想の持ち主でないことを
確認するのに利用される程度だと思われます。
一方で、国公立の後期入試や私立大学では
小論文がメインとなっている大学もあったりします。
前期入試から後期入試までの間に大きく力を伸ばすことは難しいので
あらかじめ少しずつ勉強していくことも大事です。
『面接』
唯一面接試験が課されていなかった東京大学理科3類の入試においても
近年面接が採用されたことによって、
すべての大学の医学科受験で課される試験科目となりました。

一方で、得点化するかしないは大学によって異なり、
またその点数についても各大学で大きく異なります。
近年は得点化している大学が多くなってきたため、
重要な試験のひとつになってきたことは間違いありません。
医学科入試において存在感を増す一方で、
高校の授業で扱われることがないため、
自ら積極的に先生にお願いして
練習していく必要があるでしょう。
最後に…
さて、今回は医学科入試における科目についてまとめてみました。
高校生のうちから意識しておかないと、いざ出願となった際に
自分が条件を満たしていないことに気づいても
もう取り返しがつきません。
医師を目指す高校生の皆さんは
早いうちから受験科目について意識しておきましょう!!
今回は以上です。See you。